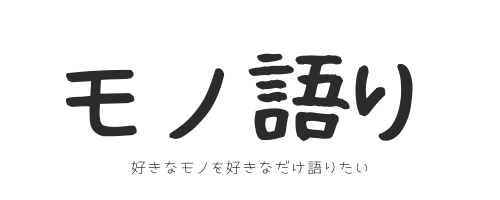どうも、広く浅いオタクの巳あくたです!
こんかいはブレイディみかこさん著作の「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について語りたいと思います。
イギリスに住む日本人の目から見たリアルで残酷な「多様性社会」をつまびらかに描いた本作の、魅力を徹底解説いたしますのでぜひ最後までお付き合いください!
物語の簡単な紹介
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」は、作家ブレイディみかこさんによるエッセイです。
物語は、ロンドン在住の日本人であるブレイディみかこさんと、アイルランド人の夫との間に生まれた息子を中心に描かれていきます。
彼女の息子はカトリック系の名門小学校で生徒会長を務めるほどの優等生。しかしそんな彼が進学したのは荒れた地域にある「元底辺中学校」。
これまでとは180度違う環境に身を置くことになった息子は、多様性の壁にぶち当たることとなります。そんな息子を見守る母の視点から、現代のイギリス社会における現実を描いた作品です。
主な登場人物とその関係
息子
主人公で、日本人の母とアイルランド人の父を持つ少年。学校では文化的な違いに悩みながらも、自分らしさを模索している。
非常に聡明で、ハッとさせる意見を述べることもしばしばある。
母親
著者であり、物語の語り手。イギリス在住の日本人で、コラムニスト。
元底辺の中学に進学した息子を通して、本当の意味で「多様」な社会を目の当たりにし、その複雑さをエッセイという形で描いている。
書評:『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が心に残る理由
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、リアルな文化的葛藤をダイナミクスを描くことで、その複雑さをつまびらかにしています。
異文化とは国と国との間にだけあるものではなく、ときに同じクラスの隣同士の間でも存在しうるのだと、痛感させられる描写が印象的でした。
だって「差別表現を連発する美少年」という濃すぎるキャラクターが隣の席に座っているなんて、日本じゃなかなか遭遇しえないシチュエーションですよね?
でもそんな冗談みたいな状況が当たり前に存在するのが多国籍国家であり、ひいては多様性社会の実態なんです。
「多様性が無い」だの「多様性を重んじろ」だのと気軽に叫ばれる昨今ですが、この本を読んだ後だとなんとも陳腐な意見に聞こえます。
「なぜ差別はなくならないのか?」「多様性とはなんなのか?」そんな永遠のテーマとも呼ぶべき疑問の答えが、ぼんやりと輪郭程度はつかめるのが本作の魅力です。
著者のスタイルとテーマ
ブレイディみかこさんは自身の経験を元に、真実味と感情を込めた物語を描き出します。
テーマとしては、文化の違い、アイデンティティの探求、そして社会的な問題が中心となっています。どれもテーマとしてはありふれていますが、彼女は自身の言葉で語り、非常に主観的であり、だからこそこれ以上ないほどの説得力を持たせているのが特徴。
エッセイという手軽な形態をとっていますが、そのエピソードの一つ一つが「多様性社会の難しさ」を如実に表しています。
どこか他人事としてとらえがちな社会問題が、グッと身近に引き寄せられるような感覚がしました。
この本の読み方ガイド:『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を深く理解するために
この本を読む前に、異文化間の摩擦やアイデンティティの問題についての基本的な知識があると、物語の背景をよりよく理解できるでしょう。
また、イギリスと日本の文化的な違いについて知識を持っていると、物語のテーマがさらに明確に感じられます。
理解を深めるためのヒント
本作はあくまでもエッセイ。作中に生じるテーマや問題に、明確な答えや、はっきりとした著者の見解が示されるわけではありません。
だからこそ、より登場人物の気持ちになってゆっくり考えてみることが大事だと思います。
息子や母の視点や感情に注目しながら、異文化間の違いが二人の人生にどのように影響を与えているかを考察してみたください。
まとめ
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、異文化間の葛藤やアイデンティティの問題に興味がある人には特におすすめです。
また、家族や社会的な問題に対する洞察を深めたい人にも最適。
読んでみて「もし自分だったら・・・」と考えてみることが、本作を楽しむ上でのいちばんのコツです。